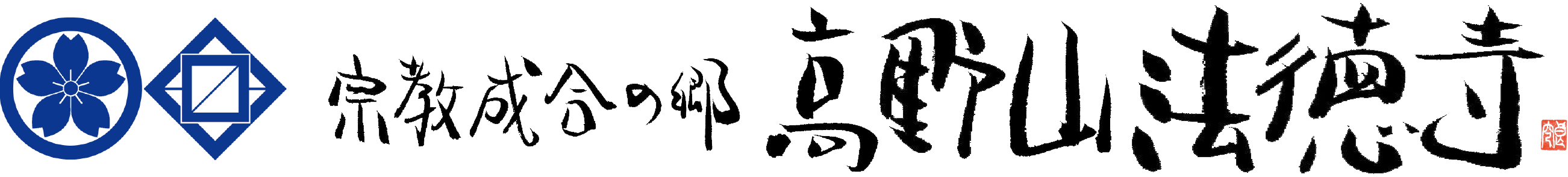あなたが生きる道
作詞・作曲 大西良空
昨日はすでに去り 明日はまだ来ない
人はみな 今を生きてゆくだけさ
過去から未来へと 絶え間なく
灯されて 運ばれて ゆくいのち
だから いま泣くよりも 笑って生きるのさ
それがこれからあなたが 生きてゆく道だから
来る人がいれば 行く人もいる
出会いと別れが 交叉する
その繰り返しの ひとこまで
泣いて笑って また泣いて
だから いま嘆くより ゆるして生きるのさ
それがこれからあなたが 生きてゆく道だから
赤い花もあれば 白い花もある
色はそれぞれ ちがうけど
あなたはあなたの ままでいい
あなたにしかない 色がある
だから うつむかないで 胸を張って生きるのさ
それがこれからあなたが 生きてゆく道だから
だから 涙をふいて 大空を見上げるのさ
それがこれからあなたが 生きてゆく道だから
臨死体験がもたらしたもの
人間は死んだらどうなるのか。死後の世界は有るのか無いのか。これは、人類にとって最大の謎であり、これからも永遠の謎であり続けるでしょうが、その謎の解明に挑まれたのが、ジャーナリストの立花隆氏です。
立花氏は、医師から死を宣告されたにも拘らず、再び息を吹き返した数多くの臨死体験者を取材され、死後の世界の解明に挑まれましたが、その結果、あの世が有るのか無いのか、結局のところはよく分からないという結論に到達したと、その著書『臨死体験』に書いておられます。
しかし、同時に分った事が二つあるとも書いておられます。
一つは、死ぬ事が怖くなくなった事、もう一つは、死はいつか必ず来るのだから、生きている内はそんな事を考えずに、いかに生きるかを考えなければいけないという事です(以下、同書から引用)
実を言うと、私自身としては、どちらの説が正しくても、大した問題ではないと思っている。臨死体験の取材にとりかかったはじめのころは、私はどちらが正しいのか早く知りたいと真剣に思っていた。それというのも、私自身、死というものにかなり大きな恐怖心を抱いていたからである。
しかし、体験者の取材をどんどんつづけ、体験者がほとんど異口同音に、死ぬのが恐くなくなったというのを聞くうちに、いつの間にか私も死ぬのが恐くなくなってしまったのである。
これだけ多くの体験者の証言が一致しているのだから、多分、私が死ぬときも、それとよく似たプロセスをたどるのだろう。だとすると、死にゆくプロセスというのは、これまで考えていたより、はるかに楽な気持ちで通過できるプロセスらしいということがわかってきたからである。
そして、そのプロセスを通過した先がどうなっているか。
現実体験説のいうようにその先に素晴らしい死後の世界があるというなら、もちろんそれはそれで結構な話である。しかし、脳内現象説のいうように、その先がいっさい無になり、自己が完全に消滅してしまうというのも、それはそれでさっぱりしていていいなと思っている。
もっと若いときなら、自己の存在消滅という考えをそう簡単には受け入れられなかったかもしれないが、いまは、ある程度年をとったせいもあるのか、それほど大きな心理的障害なしに、そういう考えも受け入れられるのである。
いずれにしても受け入れなければならないものを受け入れまいとしてジタバタするのは、幼児性のあらわれであり、あまり見っともいいことではないから、しないですませたいと思うのである。
それに、いずれの説が正しいにしろ、いまからどんなに調査研究を重ねても、この問題に関して、こちらが絶対的に正しいというような答えが出るはずがない。少なくとも私が死ぬ前に答えが出るはずがない。
だから、いずれにしても、私は決定的な答えを持たないまま、そう遠くない将来に、自分の死と出会わなければならないわけである。そのとき、いずれにしろ、どちらが正しいのかは身をもって知ることができるわけである。そのことに関して、今からいくら思い悩んだとしても、別の選択ができるわけではない。それなら、どちらが正しいかは、そのときのお楽しみとしてとっておき、それまでは、むしろ、いかにしてよりよく生きるかにエネルギーを使ったほうが利口だと思うようになったのである。
「死ぬのが恐くなくなった」ということ以外に、もう一つ、臨死体験者たちが異口同音にいうことがある。
それは、「臨死体験をしてから、生きるということをとても大切にするようになった。よりよく生きようと思うようになった」ということである。
死後の世界の素晴らしさを体験した人は、生きるより死ぬほうがいいと考えるようになるのではないかと思われるかもしれないが、実際には、逆なのである。みんなよりよく生きることへの大きな意欲がわいてくるのである。
それは、なぜか。体験者にいわせると、「いずれ死ぬときは死ぬ。生きることは生きてる間にしかできない。生きてる間は、生きてる間にしかできないことを、思いきりしておきたい」と考えるようになるからであるという。
それはそうだと思う。聖書にも、「死者は死者をして葬らしめよ」とある。生きてる間に、死について、いくら思い悩んでもどうにもならないのに、いつまでもあれこれ思い悩みつづけるのは愚かなことである。生きてる間は生きることについて思い悩むべきである。
毒矢のたとえ
この文章を読んでいて、ふと私の脳裏を過ぎったのは、お釈迦様が説かれた有名な「毒矢のたとえ」です。
ある日、マールンクヤという弟子の一人が、お釈迦様に「世の中は有限ですか、無限ですか。霊魂と肉体は一体ですか、別々ですか。死後の世界は有るのですか、無いのですか。これらの様々な疑問にお答え頂けなければ、私はもうこれ以上修行する事は出来ません」と詰問したところ、お釈迦様は、「ここに、毒矢に射られた男がいるとしよう。早く毒矢を抜いて治療しなければいけないのに、この男が「矢を射た者はどこの人間で、名前は何というのか。弓の種類は何か。矢の弦や矢じりは何で出来ているのか、矢の羽はどんな鳥の羽で作られているのか。それらの疑問が明らかになるまでは毒矢を抜いてはいけない」と言ったとしたら、どうであろうか。この男は、疑問の一つも知りえない内に死んでしまうであろう。この男にとって何より大事なことは、それらの疑問を解く事ではなく、一刻も早く毒矢を抜いて、自らのいのちを救うことである」と教え諭されたのです。
お釈迦様もまた、生きている間は、死ぬ事よりも生きる事について思い悩むべきであり、よりよく生きる為にはどうすべきかを真剣に考えるべきであると、おっしゃっておられるのです。
死を直視することの意味
臨死体験者たちが、「臨死体験をしてから、生きるということをとても大切にするようになった。よりよく生きようと思うようになった」と、異口同音に語っていると言うこの事実は、非常に示唆に富んでいます。
立花氏は、「死後の世界の素晴らしさを体験した人は、生きるより死ぬほうがいいと考えるようになるのではないかと思われるかもしれないが、実際には、逆なのである。みんなよりよく生きることへの大きな意欲がわいてくるのである。」と書いておられますが、この文章を読んでいると、死を目前にした末期がんの患者さん達が語った言葉ではないかという錯覚すらおぼえます。
不治の病によって死を自覚した人々が、異口同音に、いのちに対する感動や、光り輝く世界への感動を口にし、よりよく生きたいという強い意欲を持って、残された命を、力の限り生き抜こうとしている尊い姿は、柳田邦夫氏の『死の医学への序章』に詳しく書かれていますが、臨死体験者たちの口からも、同じように生きる事への意欲が語られているという事実を見ると、死というものが果たしている役割とその存在価値が、より一層鮮明になってくるような気がいたします。
死は、よりよく生きる上において欠くべからざるものであり、命の灯は、死と結びついた時、初めてその本来の輝きを取り戻すのではないでしょうか。
その意味で、死は、死と直面している自殺者の救済とも、決して無関係ではない筈です。
私達はもう一度、死というものを、死ぬ為にではなく、よりよく生きる為に与えられているものとして、再認識する必要があるのではないでしょうか。