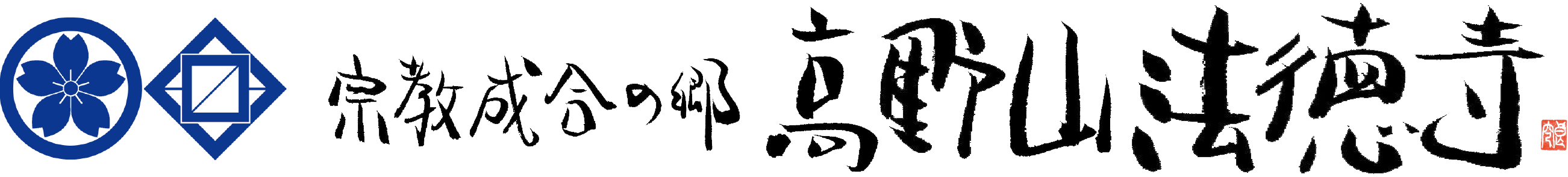ありがとうーひとさし指から奏でるしあわせ(1)
作詞・作曲 大西良空
幼き頃の夢 果たせなかったけれど
私よりしあわせな 人はいないよね
だって私は今 世界一素敵な
お母さんに愛され 生きているから
どんなに苦しくても どんなに辛くても
もう大丈夫だから 心配しないでね
お母さんが私の お母さんでよかった
あきらめも絶望も もう今日でお別れ
二度とないこの日々を 共に生きるよろこび
いつも愛してくれて お母さんありがとう
あの頃の私は 泣いてばかりいたけど
ほら見て今はもう 笑っているでしょう
だって私は今 みんなの優しさと
真心に包まれて 生かされているから
どんなに悔しくても どんなに虚しくても
もう過去をふり返らない 今だけを見つめて
すべてが私にとって かけがえのない宝物
憎しみも後悔も もう永久にさよなら
流した涙だけ 強くなれるからと
いつも励ましてくれた みんなにありがとう
どんなに悲しくても どんなに泣きたくても
明けない夜はないから 涙はもういらない
ひとさし指が教えて くれたの大切なことを
耐えること 微笑むこと すべてを許すこと
世界が輝いて 私を照らしている
今はあの先生に 言えるのありがとう
満天の夜空に きらめく星たちよ
私のこの思い みんなに伝えてね
生きる勇気をくれた あなたにありがとう
坂中さん親子の生きるための闘い
私が坂中明子さんの事を知ったのは、Facebookで紹介されていた『日本一心を揺るがす新聞の社説』(ごま書房新社)という、「みやざき中央新聞」の社説をまとめた本を通してですが、坂中明子さんは、20歳の時、予期せぬ医療事故によって、全身麻痺という重い後遺症に見舞われました。
『ひとさし指から奏でる♪しあわせ』(新水社)には、明子さんと、母親の浩子さんが、全身麻痺という想像を絶する困難な現実と向き合って来られた壮絶な日々が赤裸々に綴られています。
明子さんは、3歳の頃からピアノを習い始め、地元の宮崎女子高の音楽科から、宮崎女子短大の音楽科に進学し、母親の浩子さんが主宰するピアノ教室で子供たちの指導をしながら、ピアニストを目指していました。
ところが、短大を卒業し夢の実現に向けて船出しようとしていた矢先の平成7年(1995)9月5日の夕方、微熱があるというので、掛かりつけの医院に点滴を打ちに行ったところ、その最中に突然呼吸困難となり、心肺停止状態に陥るという思いもよらぬ医療事故に見舞われたのです。
明子さんには、元々喘息の持病があり、高校2年の時、飲んだ錠剤が原因で呼吸困難に陥った事があったため、掛かりつけの医師から「その錠剤だけは絶対に飲まないように」と固く釘をさされ、家にもその錠剤だけは置かないようにしていたのですが、その医師自身が、不注意から、使ってはいけない錠剤を処方するという初歩的な医療ミスをおかしてしまったのです。
その前日にも喘息の発作が起きて点滴を受けていたので、常識的には起こりようのない医療事故ですが、その起こりえない事故が起こってしまったのです。
この医療事故によって、明子さんは、一命を取り留めたものの、20歳にして、全身麻痺という重い後遺症を背負わなければならなくなり、この瞬間から、坂中さん親子の壮絶な闘いの日々が始まったのです。
思いを伝えられない悔しさに涙する日々
心肺停止状態によって、すべての臓器がやられ、脳もかなりのダメージを受けていると考えられていたため、入院した病院の医師をはじめ、関係者の誰もが、明子さんに何を話しても理解できないだろうと考えていました。
しかし、明子さんは、全身麻痺によって、自分の意志を伝える手段を失ったため、 相手に自分の気持ちを伝えられなかっただけで、何もかもすべて分かっていました。
私は思ったことがスムーズに伝えられない。
緊張していると言葉が出ないのだ。
話しかけられても「ウン」とも「スン」とも言わないでいると、相手から「こちらの言ってること、わかるの?」なんて言われたりする。
そんなとき、「わかってるよぉーーーーだ!」と大声でわめきたくなる。
自分の思いを伝えられないもどかしさ、哀しさ、悔しさに、明子さんがどれほど涙されたかは想像に余りあります。また若干20歳で、全身麻痺という絶望的な境遇に突き落とされた明子さんが、生きる希望を失くし、死を考えるようになったとしても不思議ではありません。
母親の浩子さんは、『ひとさし指から奏でる♪しあわせ』の中で、
その頃よく、明子は私にこう言うのだった。
「お、か、あ、さ、ん、こ、ろ、し、て!」
「いっ、しょ、に、し、の、お!」
明子や私にとって、この過酷な現実を認めることは、あまりにもつらかった。
私も『死』について、真剣に考えることがよくあった。
と書いておられますが、全身麻痺という後遺症を、生涯背負っていかなければならないという過酷な現実を前にすれば、いくら頑張ろうと自らを鼓舞しても、やり場のない憤りと悔しさと悲しさの余り、挫けそうになるのも無理はありません。
お母さんが私のお母さんでよかった
それだけに、坂中さん親子の胸中は察するに余りありますが、明子さんを支え、その心を救ったのは、やはり浩子さんの深い愛情でした。
チューブにつながれた明子さんは、水をガーゼに含ませて飲ませても、むせて飲むことが出来ませんでした。
もし口から水を飲めなければ、鼻から管を通して栄養を送り込むしか方法はありませんが、それをすると、次第に体力も弱り、寝たきりになってしまう恐れがあります。
出来れば、自分の意思で水を飲んだり食物を食べたりした方がいいのですが、主治医は、「鼻腔栄養にしないと、また元の状態(心停止)になります。明子さんには何を言ってもわかりません」と言って、口から食物を入れる事を最初から諦めているような口調でした。
しかし、母親の浩子さんは、決して諦めず、何とか口から美味しいものを食べさせたいと、一人黙々と明子さんに水を飲ませる練習を続けられたのです。
そこには、親子だから必ず通じ合えるという浩子さんの強い信念がありました。
私たちは親子だ。わかり合えないこともあるが、わかり合えることもいっぱいある、と私は強く信じている。だから、私の気持ちは明子には通じるはずだ。
なのに知識だけの世界で生きている人には、目の前の現実だけがすべてなのか。
人間にとって心の占める割合がどんなに大きいか、この知識人は知らないのだろうか。
明子の心に刺激を与えることにしよう。
このまま医者の言うことだけを聞いていては、何一つかわらない。
明子には音楽がある。少なくとも明子にはこの二十一年間、魂で聴き続けた音楽があるのだ。私の気持ちが伝わらないはずがない。
浩子さんは、カーゼに水を含ませて飲ませても、むせて飲めないのは、看護師が明子さんに、水を飲むという事を意識させていないからだと見ぬき、その意識を持たせる努力を続けられたのです。
浩子さんのこの深い愛情と、必ず通じ合えるという強い信念がついに実を結び、明子さんは、やがて水を飲むという意識を取り戻し、水を飲むようになったのです。
そればかりか、おもゆや裏ごしした梅干し、具なしの茶碗蒸し、差し入れのシチューまで食べられるようになり、浩子さんの一念は、不可能を可能にしたのです。
子を思う母親の深い愛情が、明子さんの心に響かない筈がありません。
母娘2人で八ヶ岳のペンションに泊まった夜、余り声が出せない明子さんが、改まった口調で、浩子さんに「お、か、あ、さ、ん、が、わ、た、し、の、お、か、あ、さ、ん、で、よ、か、っ、た。か、ん、しゃ、し、て、い、ま、す」とおっしゃったそうですが、この片言の言葉は、明子さんのお母さんに対する精一杯の感謝の叫びだったに違いありません。